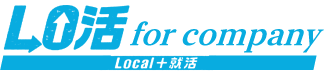中小企業採用担当者の
リアルなお悩み相談室
「内定者フォロー」はどんなことをすればよいでしょうか
回答者プロフィール

長山大助
株式会社ビスタワークス研究所 ネッツトヨタ南国 採用共育担当 http://vistaworks.co.jp/
執行役員
東京での建設資材勤務を経て、2001年にネッツトヨタ南国に中途入社。営業を経験した後、採用・教育部門に配属となる。2010年より同部門が独立し立ち上がった、採用・教育の専門会社、株式会社ビスタワークス研究所に転籍。

社⾧の想いもあり、地方の中小企業ながら、地道に新卒採用活動を続けてきたことで、なんとか内定までは出せるようになってきました。しかし売り手市場のこともあり、内定を出した学生が入社してくれないケースが少なくありません。いわゆる「内定者フォロー」について、良いアドバイスがあればお願いします。
(愛知県安城市/建設業/社員40名程度)


内定の手前にある問題を解決することで、新時代の採用活動を切り拓く
我々が暮らす高知県も、少子化や若者の県外流出が深刻な地方都市です。そのため採用環境も急速に悪化している実感があり、以前のように若者を選んで採用するということが困難になってきています。そのような環境下での貴重な内定者。絶対に落としたくない(内定辞退されたくない)ところではありますが、どの会社も同じように血眼になって採用していますので、内定=入社とはなりにくいのが実情です。
まずは内定とは何か、から考えてみたいと思います。
・内定⇒会社が決めた入社基準をクリアした応募者(学生)に出すもの
・入社⇒応募者(学生)が自分の意志で入社しようと決意するもの
ご覧の通り、内定と入社はイコールではありません。
私たち自動車販売業界でいえば、内定とは、お客様が自社で車を購入することが可能かどうかを調べる「ローンの事前審査」のようなもの。審査に通ったからといって受注報告をする営業担当者はいません。なぜなら、購入するかどうかはお客様が決めることだからです。内定という言葉は1種類しかありませんが、実態として入社確約に極めて近いものもあれば、会社が一方的に出しただけというものまであって、内定の有効性を客観視するのは極めて難しいものです。
内定承諾書をとったところで本人が入社しないと決めれば、法律的に見ても何の拘束力もありません。しかしながら採用の現場では、内定という曖昧な言葉を一つのゴールにせざるをえないという悩ましい実情があります。

学生が来ない合同企業説明会の様子

学生が来ない合同企業説明会の様子
これらを踏まえて、解決すべき課題は「内定後にフォローが必要な人(入社意欲が低い人)に内定が出てしまう」という選考プロセスにあるのではないかと考えています。そして、この課題の解決なくして今後、地方の中小企業が直面する「超少子化社会で新卒採用すること」は、一層難しくなるでしょう。
リクルートワークス研究所の調査によると、2025年卒の大学生求人倍率調査で、社員数300名未満の中小企業の求人倍率は6.5倍でした(※1)
(※1)第41回 リクルートワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)より
この調査結果を見ると、学生1名に中小企業約7社からオファーがある、超売り手市場ということが分かります。これではいくら内定を出したところで7社に1社しか新入社員は入りません。
つまり、どうしても1名に入社してほしければ7名に内定を出さなくてはいけない計算です。しかし、応募の少ない地方の中小企業で、入社してほしい人数の7倍もの内定を出すことは途方もなく困難です。
我々はこの数字の解釈を逆にして、「7社のうち1番の会社になろう!」という採用活動をしています。これは学生を選ぶ採用ではなく、学生から「御社に入社したいです!」と選ばれる採用です。これならば内定=入社に近づきますので、内定は1名に出せばOKということになります。
もちろん簡単なことではありません。当社のような自動車ディーラーは、並み居る同業他社たちと商品も価格も納期も同じという、自社で独自性を打ち出して差別化を図ることが極めて難しい業界です。
しかし、地域のお客様から「選ばれる」何かがあるから現在も存続できている。この選ばれる理由を学生向けに再定義することで「選ばれる採用」ができるのですが…、脱線しました。内定辞退の話に戻します。
応募者の入社意欲を高めるための7つのプロセス
当社では、応募者が入社意欲を高めるには、一連のプロセスが必要だと考えています。
第1段階:学生に自社を知ってもらう(企業認知)
第2段階:自社の独自性や特徴を理解してもらう(企業理解)
第3段階:自分はどんな働き方をしたいのか知ってもらう(自己理解)
第4段階:自社で働く私について考えてもらう(相互理解)
第5段階:職場体験などを経験し入社したくなってくる(動機形成)
第6段階:入社したいけど自分にできるか不安になる(不安解消)
第7段階:覚悟が決まる(決意表明=採用試験)
家や車など高価なモノを買う時や、結婚相手を決めるなど重大な意思決定をする際にも同じようなプロセスがあると考えています。この第7段階で採用試験をすれば、内定=入社にぐっと近づきますが、内定辞退の問題を抱える企業の多くは、これらのプロセスを省略した短期勝負で採用試験をしているような気がします。
昨今のネット社会を生きる若者たちの会社選びは、我々の時代よりも格段にシビアです。巷に溢れる情報を客観的に分析して、メリットの多い会社を選別するくらい朝飯前。しかし、そのメリットの多い会社で自分がイキイキと活躍できるかどうかは別問題です。これを判断するためには充分な自己理解が必要だからです。今や自己分析もネットで手軽にできる時代ではありますが、そこで分かることは身体的特徴(知能や性格傾向)を知るだけの域を出ません。
採用活動で大切なのは、「応募者にとって自社が最適な職場なのか」という相性の確認です。つまり応募者の個性と、自社の個性とのマッチングです。これが自己理解と相互理解に該当する部分で、採用活動の心臓部です。「あなたが活躍できる会社はここしかないです」と本人の自覚を促し、背中を押す手伝いが必要です。

自己理解インターンシップ

自己理解インターンシップ
当社では、入社試験で使うような本格的な適性検査を就活初期(2回目の会社訪問くらいのタイミング)の段階で学生に受けてもらい、後日、その結果を一人ずつ1時間以上かけて、全員にフィードバックします。あわせて自己理解・相互理解に特化した内容のインターンシップも開催しています。こうした取り組みから理解が深まると同時に、採用担当者との親密な人間関係もできてきます。
このような時間と手間をかけた採用は、学生が大挙して応募する大企業ではできにくいもの。一人ひとりのお客様を大切にする地域の中小企業にしかできない取り組みであり、差別化戦略でもあります。狭い地域で小売業をしている我々にとって、応募学生は未来のお客様でもあります。だから安易に不採用は出したくないのです。
出会った学生に対しては、「仲間(社員)にするかファン(お客様)にするか」以外の選択肢はありません。
一般企業よりも時間がかかる当社の選考プロセスを面倒に思い、自ら去っていく学生もいますが、それは自分の意思で決めたことですので遺恨はありません。そしてその学生は、内定を出すべき仲間候補でもなかったということです。『自分は、ネッツトヨタ南国を就職先には選ばなかったけど学生に丁寧に向き合う会社だった』という思い出が未来に繋がります。
こうした一連のプロセスを経て出した内定は精度が高く、基本的に内定=入社となるはずですが、それでも内定者を放置することはできません。「オヤカク・オヤオリ」(※2)も同様です。
(※2)オヤカク・オヤオリ
オヤカク…企業が学生に内定を出す際に、親に同意の確認を求める行為のこと
オヤオリ…内定者の親に対する企業のオリエンテーション活動

内定式

内定式
いくら試験の段階で入社意欲が高くても、内定後に家族や友人からの声掛けなどで入社意欲が削がれてしまうこともありますので、内定精度が高くなればフォローが不要になるということではありません。
しかし内定辞退されないようにするフォローと、学生の入社意欲を高めて入社前の事前準備になるようなフォローとでは目的が違いますので、実施内容も変わってくるのではないでしょうか。弱い内定を補おうとする接待のような内定者フォローは、入社したらいきなり厳しくされたように感じる「入社後ギャップ」の原因にもなります。
当社では内定者が入社して一日も早く活躍できるよう、顔見知りの先輩をたくさんつくり、先輩も入社を楽しみに待っていてくれるような関係づくり(社内のキャンプやイベントに本人や家族を招待)をする一方で、「自動車ディーラーは厳しいノルマがあるらしい…」など、親御さんの不安を払拭するための活動も実施します。

内定者のイベント参加

内定者のイベント参加
当社の社員が、自社の理念や人財育成に関する考え方や取り組みを内定者の親御さんに説明しにいき、入社式で披露する両親からの手紙を書いていただくお願いもしています。入社後に本人が壁にぶつかって思い悩んだ時に、ご家族も一緒に応援してくれるような関係づくりを目指しているのです。
*ネッツ南国は社員数約150名、年間離職率は1%~3%くらいで推移しています。

入社式の様子

入社式の様子
今後、地方の中小企業にとって、採用が容易になる未来は訪れないと思います。少しでも早く、新しい時代に合った採用活動を模索していく必要があるのではないでしょうか。
※この記事に掲載されている情報は、2024年12月にサイトに公開した時点での情報です。